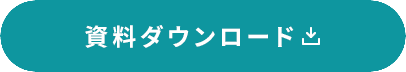- 2023年02月14日
- 有識者インタビュー
森内浩幸 先生
長崎大学医学部小児科学教室 主任教授
一般社団法人 日本小児感染症学会 理事長
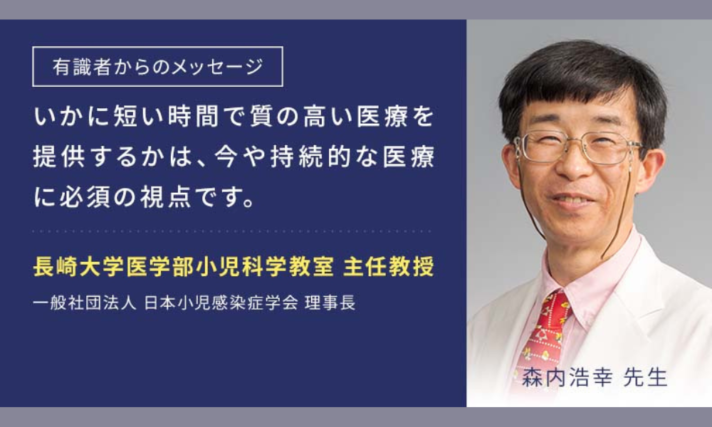
「医師の働き方改革」と「国民の意識改革」を両輪で!
長崎大学病院では、2015年から本格的に働き方改革に着手した。2019年からは、10名程度の業務ユニット(研究室、講座など)を1チームとして複数選定し、自チームの働き方改革に取り組む試み「長崎大学ワークスタイルイノベーション(WSI)」を開始しており、4年間で9チームが参加した。参加チームはコンサルタントのアドバイスを受けながら、約8ヵ月かけて自チームの課題を設定し、改革に取り組む。長崎大学医学部小児科学教室の森内 浩幸氏に医師の働き方改革への考えを聞いた。
米国で経験した効率的な働き方
医師の働き方を変える必要性はずっと言われていますが、なかなか進んでいません。2024年4月以降には、医療業界においても時間外労働の上限規制が適用され、今まで以上に残業時間の削減や業務の効率化が求められるようになりますが、働き方の実態はあまり変わっていないところが多いのではないでしょうか。
私はかつて米国に留学し診療にも携わった経験があります。米国ではオン・オフの切り替えがはっきりしており、臨床医も当番の日でなければ定時で帰って家族と食事をするのが当たり前でした。しかし、米国も最初からそうだったわけではないのです。一昔前は研修期間を中心に、ほとんど寝られないような苛烈な働き方をしていました。レジデント(本来は「居住者」の意味)は文字通り病院に寝泊まりしていました。しかし、「本当にそうした学び方・働き方がよいのか」と疑問を持って研究したグループによって、過剰労働・睡眠不足の時の認知機能や手作業の質は飲酒酩酊時と同等以下、といった研究結果が出ました。そうしたエビデンスによって「この働き方は本人のためにも患者のためにも間違いだった。システムを変えなければ」という流れになり、改革が進められてきたのです。
留学の際には、年間何百件という手術を行う外科医の仕事を間近で見たことがあります。見ていると、その人が手術に立ち会うのは一番難しい場面だけ。処置が終わればあっという間に帰ってしまう。考えてみれば、何時間もかかる手術に全部立ち会っていては、年間数百という数をこなせるわけがありません。役割分担と効率化で皆にゆとりが生まれ、結果として高いレベルの医療が提供できていたのです。もちろんそれは高い医療費という形でも跳ね返って来るのですが。
日本における医師の働き方改革においても、医療の質を落とさないことを前提に、データやエビデンスを蓄積しながら、本腰を入れて取り組まなければなりません。
医師の働き方改革、スタートは個人の意識改革
医師の働き方改革を進める上では、複数の主体があります。主だったものとしては1)個人、2)組織、3)社会・国家、があるでしょう。
1の個人がすべきことは「意識改革」です。「長時間働ける人が偉い」「遅くまで残った人が評価される」といった価値観を捨て、どうしたら短時間で質の高い医療を提供できるか、という視点に切り替えます。長崎大学病院でも、病院長がトップに立ち、長い時間をかけてこれまでの「当たり前」を疑い、効率的に働くための意識改革に取り組んできました。現場における具体的な改革活動は業務と同じくチームで行うものですから、メンバーの意識を合わせ、協力することも個人にできることの1つです。
その結果、2の組織での取り組みにおける成果が出やすくなりました。個人の意識が変わるとこれまでのやり方に疑問が湧き、前向きに業務改革に取り組めるようになります。たとえば、私たちの組織ではかつては業務時間外に参加必須の会議などが日常的に行われていましたが、今ではゼロではないにせよ、激減しました。「カンファレンスは効率化して時間を短縮すれば、日中にできそう」「院内の夜間保育、毎日は費用的に難しいけれど週1回曜日を決めてならできるかも」……。「当たり前」を疑い出すと、いろいろなアイデアが湧いてきます。新型コロナウイルス感染症の流行を経て、医療現場のリモート活用もかなり進みました。「顔を合わせなければ」と思っていた業務がリモートで代替できることを多くの方が実感したでしょう。また県内の基幹病院の院長が合同で声明を出し、「夜間や週末の病状説明」を原則廃止にすることにしました。大事な家族の病状を聴くためなのですから、家族の方が仕事の都合をつけて平日の日中に来ていただくということです。
そして、3の「社会・国家」レベルの取り組みの重要性も痛感しています。医療の効率化には、医療機関ごとの役割分担と集約化が欠かせません。若手医師の教育のためにも、とくに地方における医療機関の機能集約が必須です。しかし、医師の総数は急には増えないので、どうしてもこれまで通りの医療を提供できないケースが出てきます。“コンビニ”のように、すぐ近くで、便利に、安く、使えていた医療サービスを、これまで通りには受けられなくなる可能性がある。「享受してきた便利さの一部を手放してもらう」ことを患者さん、つまりは国民全体に納得してもらえるか。加えて、医療機関は民間企業のような経営の自由度がありません。適正な労働時間で持続的に医療を提供するために、国・政府にも、そうした事情を踏まえた支援策を期待しています。

インタビューの様子
左:コンサルタント桜田陽子 右:森内浩幸 先生
「医師の働き方改革」と「国民の意識改革」を両輪で
一方、ここ数年の新型コロナウイルス感染症の流行は、日本の医療現場の状況を国民に理解してもらう大きな機会となりました。「非常時」に対応するには、通常時に余裕を持っていなければなりません。しかし、日本の医療現場はコロナ禍前からギリギリで働いていたため、非常時にキャパシティを広げる余裕がありませんでした。旅行にも会食にも行かず、必死に現場を支えてきた医療者が、精神的にも身体的にも限界を迎え、押し寄せる患者やクレーム処理の中でバーンアウトしてしまう……。この3年間でそんな例をいくつも見ました。現場は医療逼迫の事態をよく凌いできたと思いますが、今のシステムのままでは非常時に対応できないこと、医療のキャパシティには限界があり、その全体バランスが重要性であること、多くの方がそれに気づき始めたのがこの3年だったのではないでしょうか。
「医師の働き方改革」と「国民の意識改革」、これは両輪として進めてなくてはならないし、それを後押しするための政府の政策も必要です。医師の働き方改革は、医師自身や医療機関のためだけではなく、日本の医療システムを、非常時をも含めて回していくために、待ったなしで取り組まねばならないことなのです。
誰もが休むべきときに休める社会を
意識改革の面でもう1つ感じるのは、「医療者を含めた誰もが、休めるときに休める社会を実現すること」の大切さです。今回の新型コロナウイルス感染症流行においても、仕事を休めないために無理して職場に行ったり、子供の体調が悪そうなのに保育園に預けざるを得なかったりして、結果としてクラスターが発生した、というケースが多々あると思います。
具合が悪ければ仕事を休む、子供の具合が悪ければ親が休んでケアする。そうした「当たり前」が受け入れられる社会にならないと、この先も必ず来るであろう非常時に立ち向かえません。これは社会全体の「ゆとり」でもあります。
医師の働き方改革は、社会全体の働き方改革と結びついたものであり、国民全員の問題でもあることを広く知ってほしいと思います。政府やメディアだけでなく、私たち医療者自身もしっかり伝えていかねばならないでしょう。
小児科における働き方改革プロジェクトの成果
私の所属する小児科は、2021年に「長崎大学ワークスタイルイノベーション(WSI)」に参加しました。プロジェクトでは最初にチームごとの「課題」を話し合います。病院は部門ごとの特性が大きく異なり、解決したい課題も異なります。まず医局として目指すべき「ゴール」を忌憚なく話し合えたことがよかったと思います。ここで出てきた意見をもとに、当直帯前後の勤務負担の軽減やカンファレンスの進行の簡易化などの具体的な変化を生み出すことができました。
働き方改革がもっと進めば、これまでフルタイム勤務が難しくて休職している育児中の医師や定年後の医師などに働く場を提供できるかもしれないと期待しています。。
まずは情報収集と土壌づくりを
これから働き方改革に取り組む、という医療者の方は、まずは情報収集からはじめるとよいでしょう。「ほかの病院は何をしているのか」「こんな困り事の解決事例はないだろうか」と探せば、多くの事例が見つかります。長崎大学病院も、これまでの働き方改革の成果を失敗例も含めて積極的に発信しています。
そして、もう1つ大切なのは「誰もが安心して思っていることが言える職場づくり」です。1人ひとりの思いは違って当たり前であり、年齢やジェンダーや職位によって率直に意見が言いにくかったり、意見が聞き入れられなかったりする状況は避けるべきです。そのためには組織のトップやリーダーが率先してメンバーの意見をフラットに受け止め、共に考え・建設的に話合う姿勢を示すことが大切です。難しればコンサルティング会社など、外部の協力を仰ぐことも効果的でしょう。
私たちの組織をはじめ、地方の大学病院は長年人手不足に悩んでいます。大都市や海外との人材獲得競争に加え、この国で質の高い医療を持続的に提供していくうえで、医師の働き方改革は避けては通れないものなのです。
インタビュアー:コンサルタント桜田陽子

森内浩幸 先生
長崎大学医学部小児科学教室 主任教授
一般社団法人 日本小児感染症学会 理事長